「時は、ついに満ちる」
「ネルフの妨害を排除する」
「それは」
「それは」
「始まりだ」
「そう、いよいよ始まりの時だ」
「我らの目的のため」
「人類の再生のため」
「そのためには、あえて汚名をも受けよう」
「今日の汚名は、明日の名誉となる」
「我らの目的は」
「我らの目的は」
「一つ」
「計画を、遂行する」
And live in the world forever
第14話:巨竜たちの鎮魂歌
1200時 マリアナ諸島東方海上
戦艦<モンタナ>CIC
晴れ渡った空の下、艦隊は一糸乱れぬ単縦陣をとって海原を進んでいた。
戦艦<モンタナ><甲斐><相模><ロジェストヴィンスキー><ガングート><メイン>の6戦艦を中心に据え、、護衛の巡洋艦、駆逐艦が両脇を固めるように進んでいる。水平線の向こうには輪形陣を敷いた空母部隊が遊弋し、艦載機の離発着訓練を行っている。
国連軍太平洋艦隊。
洋上に展開する艦艇の群は軍事評論家が眺めたならば感嘆すべき技量を持って訓練メニューを消化しつつあり、それは艦隊司令として暫定的に少将に任官されたマッキンレーを満足させうるものだった。
戦艦<モンタナ>に将旗を掲げた彼は(従来の任務であった空母「テンペスト」艦長職は副長が代行している)、航空母艦の艦長という職務からは想像しがたいことに、筋金入りの大艦巨砲主義者として名の通った存在であった。セカンドインパクトに伴う第四次湾岸戦争では国連軍ペルシャ湾派遣艦隊に中佐・戦艦砲術長として従軍、灼熱のペルシャ湾でイラク軍の巡洋戦艦「ネブカドネザル」と砲撃戦を演じたこともある。そんな彼が太平洋艦隊司令官への就任に当たって将旗を<モンタナ>に掲げたのは、至極当然といえるだろう。
洋上に響く主砲発射の轟音。標的に向かって射撃を繰り返す数隻の戦艦群。それはさながら、獲物に向かって火を吐く巨竜の群にも似ていた。
「<ガングート>、第8斉射。全弾遠弾。未だ命中弾なし」
「<相模>、第12斉射。1番、4番、7番命中。残弾も目標を夾叉」
「やはり、訓練時間の差だな。射撃速度も命中率も、段違いじゃないか」
CIC(中央戦闘指揮所)で訓練の様子を眺めていたマッキンレーは、ソ連海軍の戦艦<ガングート>と海上自衛隊の甲型護衛艦(自衛隊で言う戦艦の区分を指す)<相模>の砲撃結果を聞いて小さな舌打ちを漏らした。
「仕方ありません。海上自衛隊に比べて、ソ連海軍は全般的にその・・・・いろいろと問題がありますからね」
太平洋戦争の時代から、日本海軍に比べてソ連海軍の技量はお世辞にもよいとはいえなかった。むしろ、海軍士官の間ではイタリア・フランスと並んで下から数えた方が早い、という程度のレヴェルとして認識されている。その伝統は70年近くたった今でも変わってはいない。幕僚は暗にそう言っているのだった。
「まあ、<ロジェストヴィンスキー>のように、我々の訓練プログラムによって技量を向上させている例もありますし、これからおいおいやっていけば・・・・」
「それでは遅いよ。戦争は起こらずとも、敵はやってくる。そのときに我々がただの役立たずにならないためには」
速急に戦力化を図らなければならない。
マッキンレーの脳裏に、先日の光景がまざまざとよみがえってくる。エヴァ六号機を輸送中に使徒襲撃を受けたあのとき、エヴァとの共同作戦で使徒を撃破することができた。少なくともただのエヴァンゲリオンの運び屋ではないことを実証して見せたのだ。
「次こそは、我々も立派な戦力となることを証明してやる」
そして、低くつぶやく。
「できれば、使徒相手に、だがな・・・・」
幕僚の表情が、それを聞いた瞬間にわずかに曇った。
「やはり、閣下は現実に起こるとお考えで?」
「・・・・ああ。それも近い将来に必ずな」
苦々しげな肯定。マッキンレーはつい先頃の光景を思い出しながら、そう認めざるを得なかった。
ゼーレ。そしてネルフ。ジオフロントで目撃した会話の一部始終。
二つの組織の決裂。
そしておそらくは始まるであろう争い。
人と人同士の・・・・血塗れの殴り合い。
艦隊に戻った後、マッキンレーは艦隊の全艦長と首脳を集め、今後の経緯についてありのままを告げた。我々は近いうちに、使徒ではなく人を相手に戦うことになるだろう、と。
「確かに閣下の言うことを私も伺いました。しかし・・・・小官には正直実感がないです。セカンドインパクトの前後以来、人間同士の戦争は形の上では息を潜めていましたから」
「私だって、それは同じだ」
しかし、やがて事実に直面することになる。
「いやむしろ、この十数年の膿が一気に噴出する恐れもある。押さえつけていたくさびがはずれたとき、あふれ出る奔流は恐ろしいほどの勢いを持っているからな」
「・・・・」
「だからこそ、そのときの心構えだけはしておかねばならない」
現実に向き合って初めて、その過酷さが理解できるというものだが・・・・・。
頭を一つ振ると、マッキンレーは努めて明るい声で幕僚に問いかけた。
「大西洋艦隊との会合時間は?」
「はい、4時間後です」
「そうか、ではそろそろ、訓練プログラムを切り上げてくれ」
「了解しました」
幕僚は敬礼を一つ返してCICをでていく。彼はその背を見送りながら、小さなため息をついた。
まったく、イラク人相手に主砲撃ってた頃が懐かしい。あのときは誰が敵か味方かはっきりしていたというのに。それが今ではどうだ。だれが敵か味方か、まず探すことから始めなければいけないなどとは。
再び、彼は大きなため息をついた。ああ、まったくいやなものだ。
「二つの艦隊が一つになる」
「エヴァを仕掛けるか?」
「いや、いきなりそれは無粋というものだ」
「そうだ。それでは興がそがれるというもの」
「はじめは、まああれに任せるとするか」
「どこまでやるかは、わからぬがな」
「まあ、それも一興」
「そうだな」
1550時 マリアナ東方海上
戦艦<モンタナ>CIC
レーダーに反応のあった大西洋艦隊が水平線の彼方に姿を現したのは、太陽が中天から名残惜しげに傾き始めた頃であった。
戦艦<ホーンブロワー>を旗艦に、戦艦<マッケンゼン><クリストフォロ・コロンボ><テレメーア><セント・アンドリュー><ニューハンプシャー><フランチェスコ・モロシーニ><ガスコーニュ>の8戦艦を中心に据え、空母5,巡洋艦12、駆逐艦20を従えている。
「両艦隊併せて戦艦14、空母8。まさに空前の艦隊ですね」
ディスプレイに映し出された空前の艦艇数に、興奮を抑えきれない表情で幕僚の一人がそうつぶやいた。
これほどの艦隊規模を実現させたのは過去に一度きり、太平洋戦争時のアメリカ合衆国しかあり得ない。そして艦隊戦力という面においては、その合衆国艦隊を遙かに凌駕している。彼が興奮するのもある意味至極当然のことだった。
「ハルゼー中尉、口を慎みたまえ。作戦配置中だぞ」
主席幕僚のハインライン中佐がそうたしなめ、ハルゼー中尉は赤面して口を閉じる。マッキンレーはそんな様子を苦笑いとともに眺めていたが、やがて居住まいを正して、
「ハインライン中佐、通信回線を開いてくれ。相手の司令官と話がしたい」
「了解しました」
数十秒の後、<ホーンブロワー>と接続された正面ディスプレイに、海軍士官の厳つい顔が現れた。
マッキンレーはそれを見て、驚きを隠せない表情で軍帽を脱ぐ。
「トンプソン中将、あなたでしたか、派遣艦隊の指揮官は」
「久しいな、マッキンレー大佐・・・・いや、今は少将か」
「おかげさまで、なんとか将官になりました」
照れくさそうに頭をかきながら、マッキンレーは応じる。
「士官学校時代には想像もできなかったな。貴官の指揮下に入ろうなどとは」
合衆国とイギリス連邦の海軍士官学校交流プログラム。その一環として派遣された米国士官の一人に、マッキンレーが含まれていた。そして当時のイギリス海軍士官学校の教官の一人に含まれていたのが、ほかならぬトンプソンだった。
「国連海軍の指揮権上、閣下には申し訳ないですが・・・・」
「いや、かまわんよ。これも仕事のうちだ」
そう言って、トンプソンは苦笑いを浮かべる。
その表情にいささか疲れの色が混じっているようにマッキンレーには思え、わずかに眉をひそめた。
「太平洋は大西洋に比べて波は穏やかですが暑いですから。閣下もお体にはご留意なさってください」
「・・・ああ、わかっている」
自らの表情からそう言う台詞がでてきたことを悟ったのだろうか。トンプソンは肉厚の手で自らの顔をなでると、軽くそう流した。
「しかし、<ホーンブロワー>を持ってくるとは、上もかなり張り込んでいますね」
「・・・・それは、彼らも本気だということだよ」
戦艦<ホーンブロワー>。かつて世界の7つの海を制覇した大英帝国の末裔が、再びその威信をかけて送り出した最新鋭の戦艦。そしてセカンドインパクト後に建造された最大の戦艦でもある。長砲身の65口径16インチ(40センチ)砲を搭載し、より大口径の主砲を搭載した他国の戦艦と同等、もしくはそれ以上の戦闘力を誇っている。
「たしかに、我々としてはその方がありがたいですが、大西洋の防衛に関しては・・・・」
マッキンレーが危惧しているのは、太平洋に主力を集中させるあまり、大西洋の防衛がおろそかになるのでは、ということだった。
事実、大西洋艦隊の派遣内容を見るに、主力のほぼ8割が今回の回航に含まれている。残っているのは旧式戦艦や空母などで、もし仮に使徒が大西洋上に出現した場合、それを阻む兵力は存在しないに等しい。
「この戦いで、彼らは片を付ける気だ。だからこそ、我々の主力をこっちに持ってきたのだ。大西洋の防衛は、敵があちらに現れないので大丈夫だろうと言っている」
「艦隊司令部の希望的観測ですか。いつもそれですな」
それに関しては、トンプソンは何も言わなかった。
「まあ、確かに今回の戦いで片を付けてほしいものです」
可能であれば、人同士が争う前に・・・。
「ところで・・・中将」
そこで、彼は声のトーンをわずかに落とした。
「今回の回航中にその・・・・何かおかしなことは起きませんでしたか?」
「おかしなこと??」
「ええ、乗組員のサボタージュですとか・・・・その・・・」
トンプソンはその質問にわずかに眉をひそめた。
「艦隊の内部に何かおかしな動きがあるか、ということか?」
「まあ、有り体に言ってしまえば・・・・彼らにとっては、いきなり慣れない環境に放り込まれるわけですし・・・」
さすがに面と向かって艦内にゼーレのスパイがいる可能性を問いただすわけにはいかない。それ故にこういった言い回しになったのだが、かえってそれはトンプソンの不興を買ったようだ。
「その心配ならば、全くの無用だ。我々大西洋艦隊に、そういう不心得者はただの一名もおらん。全員が私の指揮下で乱れなく動いている」
彼は少しばかり不機嫌な表情でそう返答する。
「そうですか。いえ。失礼しました」
マッキンレーはそれを聞いて、わずかに内心で安堵する。と同時に、ここですべての事実を伝えることのできない歯がゆさがもどかしかった。
通信回線を通してでは、誰に聞かれるかわからない。速急に合流して、中将にも事情を説明しなければ・・・。
「では、中将、艦隊を合流させた後に、こちらにおいで願えますでしょうか? 今後の方針その他についてお話ししたいことはいろいろありますから」
「ああ。細かい詰めについては幕僚に任せよう」
「はい。それと・・・・」
合流時期は艦隊がもっとも混乱する時間である。何時現れるかもしれない敵に対する備えは、十分にしておかなければならい。
そうマッキンレーが告げようとした瞬間。
画面の向こうで、トンプソンが驚いたように画面から視線をはずし、横を向く姿が映った。心なしか、画面の向こう側がわずかに震動しているように見える。
同時に、CICのレーダー手、ソナーマンから
「<ホーンブロワー>前方海面で爆発音!」
との報告が入る。
「使徒か?」
「わかりません。水中がかなりかき乱されてしまって」
「閣下!」
「被害の有無を確認、艦隊進路を至急変えろ! ・・・少将、すまんが話はここまでだ」
「・・・はい」
「できれば、またあとでな」
矢継ぎ早に言葉を浴びせると、トンプソンの顔はあわただしく画面から消えた。
マッキンレーは最後のトンプソンの言葉に何か引っかかるものを感じたのだが、
「対潜チームを出す。ソナーは水中の異常を見つけたらすぐに報告しろ。全艦隊、砲雷戦用意!」
その疑念は、傍らのハインラインに矢継ぎ早に命令を下す間に忘却の縁へと追いやられてしまった。
1605時 マリアナ東方海上
戦艦<ホーンブロワー>
船体が大きく傾ぐ。<ホーンブロワー>のCICではトンプソンが正面ディスプレイを食い入るように見つめている。大西洋艦隊は右に舵を切り、爆発海面を左舷に見る進路を取っている。
「マッキンレーが少将・・・・か」
トンプソンは、誰に言うとでも無く小さくつぶやいた。
「士官学校の頃は、まだまだケツの青いひよっ子だと思っていたが・・・・」
それだけ自分が年をとったと言うことか。
よくよく考えてみれば、彼にむかって海軍の初歩を説いたのは、セカンドインパクトのさらに以前・・・・もう25年も前ではないか。
輝く瞳を持つ少年は、そして今は艦隊司令長官となった。
マッキンレー士官候補生、さて敵に対して、どう動くか、お手並み拝見と行こうか。
トンプソンは体がわれ知らず震えてくるのを押さえきれなかった。
セカンドインパクト以来、大西洋艦隊が初めて迎える実戦の場。様々な局地紛争を経てきたトンプソンにとっても、実に10年近いブランクがある。
たとえどれだけ訓練を積んでいようとも、一度の実戦で得られるものは大きい。そして一度実戦を覚えたものが、再び戦いに望む時の感覚。
そうだ、この感覚こそが、私の望んでいたものなのだ。
トンプソンは一糸の乱れなく動く艦隊を見て、会心の笑みを浮かべた。
・・・・おそらく、この一連の戦争が私の最後の戦いになるだろう。あとはしばらくの予備役と、その後の再就職がまっているのみ。何の希望もない世界だ。
ならば、せいぜい今を派手に楽しむとするさ。
・・・・たとえ、どんなことがあろうとも。
「全艦、左舷砲雷撃戦用意!」
戦艦<モンタナ>
マリアナ東方海上
しばしの間は、何も起こらなかった。
大西洋艦隊は爆発海面を避けるように進路を変えている。一糸乱れぬその動きに、マッキンレーはさすがはトンプソン教官、と感心していた。
そして同時に、暗鬱たる思いに捕らわれる。
・・・・相手は、確実に使徒ではない。
マッキンレーは現状から、そう判断した。
あまりに今までの使徒とは状況が違う。そもそも艦隊から離れた海面で爆発をあげるなど、自分がそこにいることを暴露するようなものだ。使徒ならば、そんな間抜けなこと、あるいは策略紛いなことはしない。もっと生物の本能に任せて、直接的な攻撃をしてくるはずだ。
「ソナー、海中の状況は?」
「爆発の影響は収まりつつあります。海中に不明目標なし」
「潜水艦ではないのか・・・・さっきの爆発はなにか、わかるか?」
「魚雷ではないですね・・・・機雷、でしょうか?」
機雷?
マッキンレーはきっちりとひげ剃りのあたっている顎を撫でながら、軽い疑問に襲われた。
ここは海のど真ん中だ。機雷なんてものが普通は漂っているわけがない。昔の戦争の名残か? いや、そんなわけがない。いくらなんでも、70年も前の戦争の遺物が、のこっているわけはない。間違いなく、あの機雷は最近のものだ。
「ならば、なんなんだ?」
あたりに潜水艦はいないという。艦隊の合流をねらって攻撃を掛けるならば、近海に潜水艦を潜ませて置いて魚雷を使うのが至極当然だろう。こちらもそれを予想しているのだが、そうではないようだ。
ならば・・・・。
そこまで考えて、マッキンレーは何気なくスクリーンに視線をあげた。そして、
「・・・・・?」
一度目をこすった。二度、三度と目をこすり、そこに映し出されている状況に間違いがないかを確認する。位置、距離。間違いない。そして脳裏を襲う衝撃。
彼は司令官用の椅子から突如立ち上がると、割れんばかりの大声で命令した。
「艦隊進路変更、左舷90度だ。右舷砲撃戦用意、急げ!」
ちくしょう、そういうことか。
マッキンレーは奥歯を嫌と言うほどかみしめた。
なぜ今まで気づかなかったのだ。
激しい後悔が襲いかかる。他人には偉そうな台詞を吐きながら、自分が一番認識していなかったんじゃないのか。これではまさに道化師だ。
「閣下、どうなさったのですか?」
ハインラインが、訳が分からないと言う顔つきで問いかけてくる。
何をそんなに焦っているのですか?
その顔つきに、マッキンレーは指を突きつけ、そしてうなった。
「ディスプレイを見てみろ!」
言われたとおり、ハインラインは視線をディスプレイに向ける。
そこには太平洋艦隊と大西洋艦隊の各艦船をアイコン表示にしたものが映っている。ビジュアルさを全く廃し、周辺の島は線で、各艦は丸いアイコンで表示されている。転舵を終えた大西洋艦隊、そしてマッキンレーの命令によって進路を変えようとする太平洋艦隊。相互の距離はまだ35000メートルほどあり、両艦隊が交錯することはない。
「・・・・ん?」
ハインラインは、目前の光景に何か違和感を感じた。
何がおかしいのだ?
艦隊行動はきわめて迅速に行われている。
敵艦隊は未だつかめず、ディスプレイ上だけを見れば、まるで両艦隊が相互を敵とする演習を行っているようなものだ。
演習・・・?
「そうだ! 我々は大西洋艦隊に進路を押さえられた! T字を描かれたのだ!」
ハインラインはその言葉にはっと気づいた。同時に、顔から血の気が引いた。
大西洋艦隊は<モンタナ>の進路を押さえるように横に展開している。
もし「彼ら」が敵だとしたら、あちらは艦隊の全砲火をこちらの戦闘に集中することができる。対して我々は、前面火力だけで対抗しなくてはならない。
日本海海戦。極東の島国がロシアを相手に戦った戦争末期に、連合艦隊を率いた司令長官が今回と同じように、敵艦隊の目前で艦隊進路を変え、自軍を圧倒的に有利な状況に置いたことがある。以来「T字を描く」とは、各国海軍の指揮官にとっては一種の憧憬と同義の言葉になっていた。
「すると・・・・すると・・・・」
「そうだ、我々は欺かれた! 大西洋艦隊は援軍ではない、侵攻部隊だ! 彼らが、我々の戦う敵なのだ!」
その言葉と同時に、レーダー手が悲痛ともいえる報告を叫んだ。
「大西洋艦隊発砲! 距離3万8千、目標、当艦隊!」
戦艦<ホーンブロワー>
マリアナ東方海上
「さすがに気づいたようだな」
トンプソンは進路を変更する太平洋艦隊を見て、満足げな笑みを漏らした。
爆発した機雷は、大西洋艦隊によって流され、そして彼らによって爆発させたものだった。マッキンレーに疑われる前にT字を描く。そのための手段の一つとして幕僚が提案したものだった、姑息だが、それなりの効果はあったようだ。
そうだ。そうでなければおもしろくない。
足下からの衝撃。主砲発射のショックで、艦は激しくふるえる。トンプソンはさらに笑みを浮かべると、傍らのマイクを通して命令した。
「敵艦隊は我々と同じ進路を取るつもりだ。各艦は事前目標の通りに射撃を開始せよ。空母部隊は防空戦に徹し、艦隊への攻撃は行うな」
艦隊は戦艦の主砲でうち砕いてやる。つまりは、トンプソンもマッキンレーと同じく大鑑巨砲主義者だったということだ。
<ホーンブロワー>が第4斉射を放つ。双方の距離は3万5千のまま一定している。彼は正面ディスプレイの、自分の旗艦からのびていく一本の線をじっと眺めていた。その線がモンタナのアイコンと交叉したとき、レーダー手が歓喜の声とともに報告する。
「第4斉射、敵艦を夾叉!」
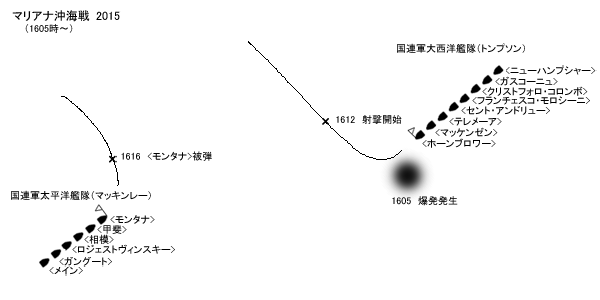 戦艦<モンタナ>
戦艦<モンタナ>
マリアナ東方海上
CICに主砲発射のそれとは段違いに激しい衝撃が襲いかかり、マッキンレーは両足を踏ん張ってそれに耐えなければならなかった。ハインラインは近くのものに捕まりながら、「状況報告!」と叫んでいる。
「船体左舷に至近弾、6番高角砲群、全滅!」
「機関全力発揮可能」
「各主砲、射撃管制装置異常なし」
「敵艦隊との距離は」
「3万4500、徐々に接近中」
「閣下!」
ハインラインの叫びに、マッキンレーはうなずきを返した。
「全艦、敵艦隊に射撃開始!」
もはや、彼は相手を大西洋艦隊とは呼ばなかった。
これが、決めなければならない覚悟か。
だとしたら、あまりに神とは惨いものだ。
1625時 マリアナ東方海上
<モンタナ>の被弾と太平洋艦隊の射撃開始は同時期だった。
一番砲塔前面の甲板を食い破った<ホーンブロワー>の一発は鋲鎖庫を破壊し、そこにいた兵員を血塗れの肉体に変えたが、それ以上の被害を与えることはなかった。
その報復とばかりの旗艦の発砲にあわせて、各の戦艦は鎌首をもたげ、炎を吐き出す。旗艦に続いてもっとも早く射撃を開始したのは2番艦の<甲斐>で、続いて最後尾の<メイン>、<ロジェストヴィンスキー>と続く。<相模>が初弾を発砲したのは<モンタナ>の第3斉射と同じ時期であり、<ガングート>が未だに一発も主砲を撃っていない理由を知る者は誰もいない。
それぞれは艦隊の航行順序に従い、<甲斐>が<マッケンゼン>を、<相模>が<テレメーア>を、<ロジェストヴィンスキー>は<フランチェスコ・モロシーニ>、<メイン>は<ガスコーニュ>をねらっている。数の差がある故、先に片づけるべき戦艦にまず目標を定めていた。
一方の大西洋艦隊だが、戦艦の数は多く、先手をとった一方で、実戦経験の無さから集弾に苦しんでいる。
<ホーンブロワー>はモンタナを夾叉したことで全力発射を行っており、初弾命中から現在までに4発の命中弾を与えている。<甲斐>をねらっている<マッケンゼン>はようやく夾叉弾を出し、3番艦、4番艦の<テレメーア><セント・アンドリュー>は相模に向けてまだ命中弾はないが次々と主砲を放っている。
一方で5番艦以下だが、イタリア戦艦の<フランチェスコ・モロシーニ><クリストフォロ・コロンボ>は<ロジェストヴィンスキー>をねらい、<ガスコーニュ>は<ガングート>を射撃している。発射速度が遅いのは誰もが納得しているので何も言わない。しかしながら<ニューハンプシャー>が未だに射撃を開始していないのには理由があった。
「なぜ我々合衆国の戦艦同士が戦わねばならないのです!」
砲術長がCIC内部で怒声を張り上げている。<ニューハンプシャー>に指定された射撃目標は同じアメリカ海軍から国連軍に参加している<メイン>だった。
「そもそも我々が太平洋艦隊と戦う理由は何ですか! 説明には納得いきません、直ちに戦闘を中止してください、艦長!」
しかし、艦長は砲術長を冷たい視線で眺めている。
「なぜ、そこまで納得しないのだ。我々は全て新しい世界の創造のために戦う。そう納得したのではないか。貴官も聞いただろう」
「ええ、それは確かに聞きました。しかしそのために太平洋艦隊と戦闘するなど・・・あそこには、あそこには私の弟がいるんです!」
「だからどうした。新しい世界のためには、犠牲は常につきものだ」
「それは違う! 犠牲を少なくして、それでこそ新しい世界は・・・・」
砲術長の台詞は最後まで続かなかった。
艦長は無言のままホルスターから拳銃を抜くと、砲術長の眉間を問答無用とばかりに撃ち抜いたのだ。
CICに猛烈な血の臭いが立ちこめる。どさり、と生気をうしなった体が倒れ墜ちる音。部屋の隅では一連の様子を見ていた少年兵が、壁に向かってしゃがみ込み、嘔吐している。
「ミッチャー少佐」
「はっ」
艦長は手に飛び散った血しぶきをハンカチで拭うとホルスターに銃を納め、何事もなかったかのように一人の士官を呼んだ。
「ハルゼー中佐は戦死だ。変わって砲術長を勤めよ」
「・・・・はい」
<ニューハンプシャー>が射撃を開始したのは、それから5分後だった。
海面は14隻の戦艦の砲弾によって沸騰せんばかりに泡立ち、所々に小山のような水柱が立っている。あたりは発砲の爆煙で薄暗く煙り、傾きつつある太陽にわずかに輪がかかっているようにみえる。
太平洋艦隊が進路を大西洋艦隊とあわせ、およそ30000メートルほどの距離で双方が平行な状態で砲火を交え始めると、命中率は格段に上がりだした。
射撃開始が遅れた<ニューハンプシャー>をのぞく全艦はすでに目標に1発以上の命中弾を与えており、さらに次々と砲弾を放っている。
<ホーンブロワー>の第10斉射が<モンタナ>を襲ったのは、<モンタナ>が今までのお返しとばかりに<ホーンブロワー>に5発をたたき込んだ直後だった。16インチ砲弾10発のうち8発は付近の海面にむなしく水柱をたてたが、残りの2発は相次いで1番、2番砲塔の側面甲板を貫き、爆発する。
CICを今まででもっとも巨大な衝撃が遅い、マッキンレーは司令官席から投げ出され、したたか腰を打ち付ける羽目になった。
「1番、2番砲塔に命中弾、前部弾火薬庫の温度が上昇しています!」
「つっ・・・・注水作業急げ、後部砲塔はそのまま射撃を継続!」
<モンタナ>級は3連装の16インチ砲を船体前後部にそれぞれ2基ずつ装備している。そのうちの半分が一挙に失われ、同時に弾火薬庫への注水によって速力は一気に落ちた。
「閣下、本艦の現状では、艦隊戦の指揮をとることは・・・・」
「・・・・やむをえまい・・・・」
打ち付けた腰の痛みに眉をしかめ、しばしディスプレイを見つめていたマッキンレーはあきらめたように肩を落とす。
「全艦に発光信号。 我レ艦隊運動継続困難ナリ、一時的ニ離脱ノタメ、以後ノ指揮ハ<甲斐>艦長ガトレ」
そのまま<モンタナ>の主砲は沈黙し、よろめくように戦列を離れた。副砲以下の砲塔群は、相変わらず戦艦以外の艦艇に向かって砲撃を続けているが。
むろん、太平洋艦隊とて叩かれっぱなしと言うわけではない。
ことに<甲斐>の働きはすさまじいものだった。戦闘開始から程なくして<マッケンゼン>に15発近い命中弾を与え、これを落伍させることに成功している。
「旗艦、離脱します!」
レーダー手の報告に、<甲斐>艦長の兄部一佐はわずかに眉をひそめた。
戦闘開始一五分で旗艦落伍。一方こちらは戦艦一隻を大破させる、か。
この調子で行くと、遠からず数の差で我々は敗れるな。何しろこちらは6隻・・・・いや、<ガングート>がただの役立たずである以上、5隻の戦艦で相手の8隻と戦わねばならないのだ。そう、だとしたらとことんまで相手を沈める必要はない、とりあえず、沈黙させればいい。
兄部は<マッケンゼン>をこれ以上叩くことに意味を見いださなかった。
「艦隊進路このまま。当艦は目標を変更する。4番艦の<セント・アンドリュー>を叩くぞ」
3番艦の<テレメーア>は<相模>と交戦中のため、無傷の<セント・アンドリュー>を叩く。その方針はCICの士官たちに抵抗無く受け入れられた。しかし続いての、
「弾種を変更する。榴弾を装填」
兄部のその命令に、艦橋は一気にざわめいた。
戦艦の装甲を貫くには、砲弾の勢いを一点に収縮して装甲を貫かねばならない。そのため装甲貫通力の高い砲弾を使う。これが俗に徹甲弾と呼ばれるものであり、今まで<マッケンゼン>を叩くために使っていた砲弾もそれだった。
ところが今兄部が装填を命じた榴弾は、装甲貫通力が低く、変わって破片、焼夷効果の高いものである。主に対地攻撃、対空射撃に使われることが多く、現状の対艦戦闘ではおよそあり得ない選択だった。
「まあ、見ていろ」
兄部は自分を見つめるいくつもの瞳に、そう答えた。
ただ単に鉄砲撃ち合うだけが、戦艦の戦闘ではないのだ。
<甲斐>の主砲が獲物を求める竜の首のように不規則に動く。相互の速度関係、あたりの風速や空気の密度、そして地球の自転など複雑な計算式が搭載されているスーパーコンピュータによって計算され、その結果が出力、さらに主砲の射撃管制システムへ入力される。ディスプレイには、射撃準備が整ったことを知らせるポップアップメニュー。
「撃ぇっ!」
砲術長はコンソールにもうけられた主砲発射のボタンを押し込み、同時に船体が激しくふるえた。
太平洋艦隊最大の18インチ砲9門が、轟音とともに砲弾を吐き出したのだ。
目標は<セント・アンドリュー>。弾着はおよそ50秒後だ。
<相模>相手に交戦していた<テレメーア>の昼戦艦橋で、チャーチル中尉は暇そうに戦闘を観戦していた。主計士官である彼にとっては、平時こそがもっとも忙しい時期であり、ある意味戦闘開始後は何もすることがないからだ。首脳部がCICに引きこもってしまったのをいいことに、彼は昼戦艦橋で司令官席に腰掛け、悠然と海戦の光景を眺めていた。
<相模>は16インチ砲を12門装備している新鋭戦艦だが、こちらは<テレメーア>と<セント・アンドリュー>の2隻合計22門の16インチ砲がある。すでに<相模>には6発を命中させており、少なからぬ浸水と副砲群全滅の戦果を挙げていた。
チャーチル中尉は<相模>の前を進む戦艦がこちらに向けて主砲を発射したのを目撃した。<テレメーア>の前を征く<マッケンゼン>が大火災を起こしながら戦列を離れて行くのは先ほど目撃している。どうやら、彼らは僚艦の救援をするつもりらしい。
金切り声をあげて飛来する砲弾。しかしそれはチャーチル中尉の予想を裏切り、<セント・アンドリュー>の周りに水柱をあげることはなかった。代わりに、空中に炎の花を9つ、盛大に咲かせる。
「榴弾?」
バカにしたように、チャーチル中尉は笑った。
あんなもので戦艦を叩こうというのか。装甲を施された戦艦に、榴弾で何ほどの被害が与えられると言うのだ。
それとも、もう徹甲弾がなくなったというのか?
やはり、日本人の思考はよくわらなんな。
しかし、続けざまに送り込まれる榴弾によって<セント・アンドリュー>の射撃速度が見る見る落ち、ついに沈黙してしまうに至って彼の顔色は変わっていった。
何だ、何が起こったのだ?
彼には事情がわからなかった。そしてその戦艦が続いて自分の乗る<テレメーア>に初弾を送り込むまで、その疑念は続いた。
兄部一佐はは目標を<テレメーア>に変更するよう命じながら、口元に会心の笑みを浮かべた。
確かに榴弾は装甲貫通力が低く、従来戦艦同士の砲撃戦には向かないと言われてきた。しかし、その「常識」が造られたのは遙かに昔。もう100年以上前の第1次世界大戦の時である。それ以降、戦艦同士の大規模な殴り合いはほとんど起こらず、それ故に過去の常識がそのまま信じられてきたのだ。
現在とその頃では事情が違う。現在の戦艦はほぼ全艦が射撃管制にレーダーを使用しており、そしてそれはほとんどが「非装甲」である。榴弾でも十分叩くことが可能だった。そして榴弾の影響範囲は、ただ目標を貫くだけの徹甲弾に比べ遙かに広い。レーダーアンテナをへし折られ、あるいは破片によって破壊されることで、射撃の命ともいえる情報は全く入らなくなる。
兄部が狙ったのは装甲の貫通ではなく、彼らの「目」を奪うことだった。レーダーさえつぶしてしまえば、戦艦は浮いているだけの存在に等しい。
まあ、臨機応変と言うところだな。
兄部はそうつぶやく。
<テレメーア>が沈黙したのは、さらに3斉射の後だった。彼らの射撃をせせら笑っていたチャーチル中尉は、昼戦艦橋の間近で炸裂した榴弾の破片により一片の肉塊になっている。兄部たちの交戦相手は、<甲斐>が<ホーンブロワー>、同じく榴弾での射撃を開始した<相模>が<フランチェスコ・モロシーニ>に移っている。
ディスプレイ上の両艦隊の動きは、さらに混迷の度合いを深めてきた。
太平洋艦隊はすでに<モンタナ>を大破させられ、さらに<相模><ロジェストヴィンスキー>が中破に等しい損害を受けている。<メイン>は幸いまだ小破程度の損害だが、気がつけば<ガングート>の姿はない。いつのまにやら沈んでいたようだ。
一方の大西洋艦隊は<マッケンゼン>沈没、<テレメーア><セント・アンドリュー>が交戦能力を失い、むなしく波間に漂っている。後続艦が続々と戦闘能力を失ったため、旗艦の<ホーンブロワー>と残余の艦の間には間隔があいており、ために効果的な連携ができない状態になっていた。<フランチェスコ・モロシーニ>は<相模>の榴弾によって叩かれ続けており、一方で<クリストフォロ・コロンボ>以下の船はあいかわらず緩慢に射撃を続けている。<ニューハンプシャー>の射撃速度はアメリカ戦艦らしく速かったが、主砲の扱いに熟練していたハルゼー中佐にかわってミッチャー少佐が砲撃の指揮を執っているため、その命中率はあまりよくない。
「やはり、彼らは役立たずだな」
「まあ、そういうな」
「試みにぶつけてみた。相手が優秀だった、というところか」
「のんびり言っている場合か? 奴らの力は、まだまだ必要になるのだ。使い捨てとはいえ、捨て所を誤るのは大いなる無駄だ」
「まあ、そうだな」
「トンプソンも、存外に無能者よ」
1655時 マリアナ東方海上
戦艦<ホーンブロワー>
トンプソンが<モンタナ>にとどめを刺すのをあきらめ、主力の戦闘海域に戻ってきたとき、彼を迎えたのは僚艦の勝利の凱歌ではなく、<甲斐>の主砲弾だった。旗艦は沈黙させるだけではいけないと踏んだのだろうか。<甲斐>の弾丸には榴弾と徹甲弾が半分ずつの割合で降り注いでくる。
トンプソンはCICで後悔に唇をかみしめた。
実戦経験の差はここまでくるのか。麾下の戦艦部隊が次々と沈黙していく。巡洋艦以下の艦艇についでも、おそらく同様の事態が起こっているようだ。
合衆国と日本の二海軍。
さすがはかつての三大海軍国の二翼が合同しているだけのことはある。
「しかし」
残る一つの座を占めていたのは我々大英帝国だ。その威信に賭けても、負けるわけには行かないのだ。そう。負けるわけには行かない。
「砲門開け、目標、敵旗艦!」
1700時 戦闘海域後方
戦艦 <モンタナ>
戦闘海域を離脱した<モンタナ>が、空母部隊の護衛艦と合流したのは<ホーンブロワー>が<甲斐>に向かって射撃を開始した頃だった。
戦況は太平洋艦隊の有利に進行している。兄部一佐の指揮はさすが、というところだった。すでに<フランチェスコ・モロシーニ>は海上になく、<ガスコーニュ>も大火災を起こしながら傾斜している。味方も<メイン>を喪失したものの、向こうとの数は3対3。そして命中率がこちらの方が段違いに高い。
横付けされた護衛艦が火災に向かって放水を開始し、あわせて工作艦が接舷を試みる。応急修理を至急行わなければ、艦を失う恐れもある。
「トンプソン中将がゼーレの側に立つとは・・・・」
CICを出て昼戦艦橋に上り、そこで作業の様子を見ながらマッキンレーは暗い表情を浮かべていた。
かつての敬愛する教官が、自分に向かって砲門を開く。そのショックから、彼はまだ立ち直っていなかった。
何らかの理由で、トンプソン中将・・・・そして大西洋艦隊は望まずして戦っているに違いない。
そう考え、自分の内心の疑念を押さえつける。
この海戦は、我々が勝つだろう。そうだ。中将に降伏を勧告してみようか。そうすれば、彼らも無益な戦いを続けるとは思えない。望まぬ戦いをしているのであれば、なおさらだ・・・・。
しかし、このときマッキンレーは気づいていなかった。
「人同士が戦うことを覚悟しなければならない」という自分の台詞を、自分自身がまだ信じていなかった・・・信じたくなかったこと。そして、彼ら・・・大西洋艦隊が何のために太平洋に出てきたか。その目的を。
知っていたならば、即座に全艦隊に撤退を命じただろう。現在の海域は、自分たち以外からの支援を受けるにはあまりに遠すぎた。
そしてそれに気づいたときには、すでに彼らの艦隊は逃れようのない罠の中におちていたのである。
爆発音とともにマッキンレーの元の乗艦である<テンペスト>が盛大な煙を上げたのは、彼が大西洋艦隊の行動理由について考え始めたときだった。
爆発は隣接する空母群にも相次いで起こる。突然の事態に空母部隊は為すすべを知らず、あたふたと動き回る。空襲と勘違いしたのか、対空砲火を打ち上げる護衛艦も出てくる始末だ。
「なんだ、今度はどうした!」
マッキンレーの疑問を解決したのは、艦橋内の誰でもなかった。
爆煙を派手に吹き上げる<テンペスト>、そして空母群。それらの煙の中から相次いで現れた巨大な影が、彼の視界に入ったからだ。
傍らで驚愕の表情を見せていたハインラインが、かすれた声を上げた。
「・・・・エヴァンゲリオン・・・・だと!」
純白に塗装され、その右手には巨大な槍を持った姿。頭部は今までマッキンレーが見慣れた初号機や弐号機と異なり、一種凶悪な印象を与える。
海中から突如現れた5体のエヴァは、3体が1隻の空母を屠り、残り2体が周辺の護衛艦に向けてその牙を剥いている。ATフィールドによって切り裂かれる巡洋艦。空母を屠ったエヴァは背中から巨大な翼を広げ、空中から攻撃を続けている。艦隊は混乱の中でも砲火を撃っているが、もとより効果などあるわけがない。
「そうか・・・・大西洋艦隊は、これを運んできていたのだな」
戦艦同士の砲撃戦に先立ち、分派された大西洋艦隊の空母部隊。そこに随伴する輸送船に、彼らは積まれていたのだろう。
だとしたら、我々に勝ち目はない。たった1体のエヴァですら、我々太平洋艦隊を赤子の手をひねるように壊滅させることができるのだから。
それが、よりにもよって5体、5体だと!
マッキンレーは顔面蒼白のまま、空母部隊がなす術なく壊滅していく様を見つめていた。
「閣下、兄部一佐に退避命令を! 戦艦部隊だけでも逃がさなければ!」
ハインラインが、呆然としているマッキンレーの肩を抱き、そういいながらがくがくと揺らした。
そうだ、戦艦部隊だけでも、逃がさなければ。
ようやくそう考え、兄部に連絡を取るべく通信手に命令を発しようとする。その瞬間、<モンタナ>の船体に巨大な衝撃が走った。
マッキンレーは反射的に外に視線を向ける。
昼戦艦橋の窓の向こうで、エヴァンゲリオンが彼を見つめていた。
その唇がつり上がり、笑みの形をとる。マッキンレーにはそれは悪魔の笑みに思え、背筋をふるわせた。傍らで、ハインラインがぶつぶつと何事かを呟いていた。「爺さんの小説に、こんな戦いはでてねぇぜ」。何のことか、マッキンレーにはわからなかった。
<モンタナ>が沈んだのは、5分後のことだった。
1710時 マリアナ東方海上
戦艦<甲斐>
「確かに、<モンタナ>は沈んだのだな?」
「はい。空母部隊も、同じく・・・・」
通信手、レーダー手の沈痛な報告に、兄部は悲壮きわまりない表情で応じた。
断末魔の<モンタナ>から最後に放たれた一片の通信文。「エヴァンゲリオン」と記されたそれが、空母部隊と<モンタナ>喪失の全ての原因を物語っていたからだ。
「おそらく、次は我々にくるだろうな」
さらりと兄部はそういい、CIC内部は水を打ったように静まり返る。
「大西洋艦隊は今後の戦闘を考えて生き残っていなければいけない。現戦場は我々の有利に進んでいる。空母部隊は壊滅し、エヴァの手は空いている。我々を襲わない理由はどこにもない」
「逃げても、おそらくは追いつかれますね」
「そうだな」
傷ついた艦隊の速度と、エヴァンゲリオンのそれを考え、兄部はその意見に肯定する発言をした。続いてそれぞれの顔を一通り見回した。正面ディスプレイの向こうには、青ざめた表情を浮かべるそれぞれの艦長の姿がある。
「さて、諸君。大西洋艦隊の目的は、確実に日本への上陸だろう。ネルフ本部を実力で制覇し、憂いを取り除くつもりだ」
「すると、艦隊は上陸前の艦砲射撃のために・・・・」
「そうだろうな、おそらく」
そうすると、我々がもっとも効率的に動くには、どうすればいい?
兄部はそこまで言葉を継がなかった。しかし、彼の内心のその問いに答えたのは、先ほど「逃げとも追いつかれる」と発言した士官だった。年の割に老けた顔立ちで、平均身長に比べ驚くほど太っている。
「言って見ろ、山口三佐」
「はい、上陸前の艦砲射撃を担当するのはおそらく大西洋艦隊でしょう。そうすると、彼らを一隻でも多く沈めることで・・・・」
「被害を少なくすることができる、というわけか」
「どのみち、我々は助かりません。ならば少しでも残る者の負担を軽減した方が」
沈黙が満ちる。
それはまさに、来るべき死を待つ死刑囚の感覚といえよう。
やがて、兄部はきっと顔を上げた。
「山口三佐の言うとおりだ。我々はこのまま大西洋艦隊のとの戦闘を継続する」
国連軍としてではない。自衛隊として、自らの国を守るために。
叫んでいるわけではない。怒っているわけでもない。淡々とした兄部の口調は、しかしCIC内部に歓声にも近い反応をもたらした。少なくとも意義を持って死に臨むことができる。これほどの喜びはないとばかりに。
「可能な限り多くの船を沈めろ。我々の今日の戦果が、明日の仲間の負担を軽減するのだ」
そしてそのまま、ディスプレイの向こうの艦長たちに視線を向ける。海上自衛隊から参加している者は、一様に兄部の台詞に応じる姿勢を診せていた。
兄部は、残りの艦長たちに向かって言葉を発した。
「と、いうことです。我々自衛隊はこのまま戦闘を継続します。しかしながら国連軍の指揮権を持つ身としては、みなさんに戦闘を強要はしません。これは命令です。各艦は極力被害をとどめて、この海域を離脱してください。そして」
この戦闘を見届け、次の戦いに経験を生かしてほしい。
ディスプレイに向かって、見事な敬礼を一つ。兄部はそのまま回線を切断すると、おっとりとした口調で命じた。
「さらに砲撃を続行。沈みそうな艦から狙って撃て。<相模>艦長に連絡を取れ。2隻で1隻ずつ片づけて行くぞ」
兄部の提案に、<相模>艦長は依存なく応じた。
<甲斐><相模>は相次いで砲門を開く。目標となったのは、傾斜する<ガスコーニュ>と沈黙したままの<セント・アンドリュー>だった。<テレメーア>は相互の艦の位置から狙うには位置が悪すぎた。砲弾を降らせてくる<ホーンブロワー>には護衛艦部隊が牽制の砲撃を間断なく打ち込む。
兄部は<ガスコーニュ>が沈没するのを確認した後、<ロジェストヴィンスキー>が戦闘に加わっているのに気づいた。
「何をしている、すぐに逃げろ!」
通信回線をつなぎざま、兄部はそう怒鳴りつける。しかし帰ってきた返事は、にべないものだった。
「我レ舵損傷。逃ゲ切レヌ」
嘘であることはすぐにわかった。確かに<ロジェストヴィンスキー>は損傷していたが、それは主に前部に集中しており、船体の尾部は傷一つついていなかったからだ。
「・・・・馬鹿どもが」
兄部は小さくそうつぶやき、苦笑を浮かべるとさらに砲撃続行を命じた。
3隻の戦艦は次々と咆吼をあげて弾丸を送り出す。それはまさしく、断末魔の巨竜たちの張り上げる叫びにも似ていた。
エヴァンゲリオンが兄部たちの戦艦に攻撃を掛けたのは、まもなくのことだった。しかしながら大西洋艦隊はそれまでに保有する戦艦のうち6隻を失い、巡洋艦、駆逐艦も多くが傷ついた。
一方の太平洋艦隊はトンプソンたちとの戦闘に加えてエヴァの攻撃も受け、結果として戦艦・空母を全て喪失。一方で補助艦艇はその多くが脱出に成功した。彼らに攻撃を加えようとする艦艇に対して兄部の<甲斐><相模><ロジェストヴィンスキー>が壮絶な抵抗を示し、多くの艦艇の脱出を援助したのだ。
代償として、エヴァにより彼らの戦艦は完膚無きまでに叩きつぶされたが。
<甲斐><相模><ロジェストヴィンスキー>の生存者は、3隻合計で5名。
そこに、兄部の名はもちろんない。
太平洋艦隊は、文字通り壊滅した。
巨竜たちは、海の底で永い眠りについた。もう、彼らが目覚めることは、ない。
続きを読む
前に戻る
上のぺえじへ
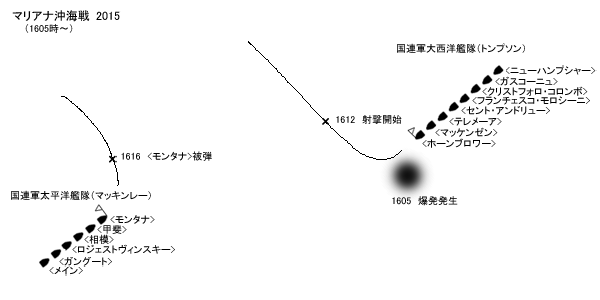 戦艦<モンタナ>
戦艦<モンタナ>