想い
- Always...with you. -
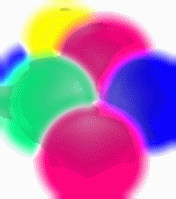
|
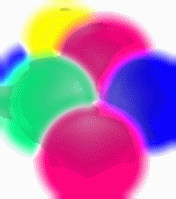
|
「えぇー!!また明日もなのぉー!!」 惣流アスカ・ラングレーは不満を隠そうともせずに大きな声で言うと、目の前の 金髪の女性、−眉が黒いところを見ると、金髪は染めたもののようだ− 赤木リ ツコに一歩近づいた。アスカのその美しい容姿は不服の表情を表していても魅力 を損なってはいなかった。 「えぇ、アスカと、それにシンジくんもね。」 リツコは白衣のポケットに左手を突っ込んだまま、右手だけでコンソールのキー ボードを素早く操作しながら、アスカの不満げな声を全く無視するように言った。 「僕もですか?」 碇シンジは特に不満というわけではなかったが、アスカの様子に引きづられたよ うな感じだ。見るからに線の細い少年。気の弱そうな態度だが、その黒い瞳には 優しさが確かに感じられる。 「そう、初号機のセンサー、交換したんだけどチューニングが必要なの。それに 弐号機の方のデータも取っておきたいのよ。」 アスカはエヴァンゲリオン弐号機専属パイロットであり、碇シンジは初号機のパ イロットである。赤木リツコはエヴァンゲリオンのメンテナンスをはじめ、運用 面での責任者だった。 「ま、そういうわけだから、悪いけど明日もガッコ、休んじゃって。」 アスカやシンジの上司でもあり保護者でもある作戦部長の葛城ミサトが軽く腰に 手をあてたポーズで言う。 「はい。」 「あぁーあ、わかったわよ。」 アスカは諦めたように答えたが、一瞬シンジの方を見て、口元に満足そうな笑みを 浮かべた。 「・・・わたしは?」 その時、それまで黙っていた少女、綾波レイが声を発した。彼女はエヴァンゲリ オン零号機専属パイロットである。プラチナブルーの髪、紅い瞳が印象的だ。 「レイはいいわ、零号機のデータは十分だし、とくに問題はないから。」 リツコが答えた。まだコンソールを操作している。視線はディスプレイの上だ。 「ファーストはいいわねぇ、余裕よねぇ。」 「・・・・・・」 アスカが言った。しかし言葉の内容に反してどこか自慢げな言い方に聞こえる。 レイは表情を変えることなく無言だった。視線はリツコの方へ投げている。 「あ、綾波、明日は来なくていいんだね。」 「・・・・・・」 シンジが声をかけるとレイが視線を向けた。シンジは微笑みながら言う。 「ここんとこ毎日だったから、その、ゆっくり休むといいよ。」 「・・・・・・」 レイは無言でシンジを見つめている。紅い瞳がなぜか悲しげに見えた。 ・・・わたし・・・ 小さな桜色の唇が微かに動いたように見えたが、言葉は出てこない。 ・・・綾波・・・なんだか元気ないみたいだ・・・ シンジはレイに何か声をかけようと思ったのだが、何を言っていいのかわからな かった。 「はぁ、じゃ、帰りましょ、シンジ!」 「え?」 アスカの声にシンジが振り向く。アスカはミサトの方を向いていて、シンジの方 には注意を向けていなかった。 「もう帰ってもいいんでしょ?ミサト!」 アスカがミサトに言う。ミサトはやれやれといった表情で苦笑いしていた。 「んじゃ、今日はこれくらいで終わりにしましょっ!!」 ミサトの声に、少年と少女、そしてもう一人の少女は帰途についた。 数分後、シンジとアスカは2人の住まいであるミサトのマンションの近くにある スーパーに居た。シンジもアスカもミサトのマンションで暮らしているのだが、 食事をはじめとする家事全般はシンジが行っていた。本来は当番制のはずなのだ が・・・ 「ねぇアスカ、今夜のご飯何にしようか?」 「そうねぇ、ハンバーグは昨日食べたし、カレーもこないだ食べたしぃ・・・」 「ミサトさんは今夜帰って来るのかな?」 「何も言ってなかったし、帰ってくるんじゃない?」 2人は食料品の売り場を歩きながら今夜の夕食のメニューについて話していた。 売り場には新鮮な野菜や、魚介類、肉類をはじめ、豊富に品物が揃っている。セ カンドインパクトと呼ばれる運命の日から15年、人類は驚異的なスピードでそ の生活環境を復旧させていた。 シンジは肉類のならぶ冷凍ケースを見てレイのことを思い出した。 ・・・そういえば、綾波は肉が嫌いだったな・・・ ・・・綾波は晩ご飯どうしてるのかな?・・・ ・・・今日なんだか元気なかったな・・・ その時、聞き覚えのある声が2人の耳に飛び込んできた。 「アスカ、碇くん!!」 2人が振り返ると、そこにはクラスメートの洞木ヒカリが笑顔で立っていた。 「あ、ヒカリー!!」 「あれ、イインチョも買い物?」 2人はヒカリの姿を見ると、笑顔で話しかけた。ヒカリも笑顔で答える。 「えぇ、碇くんとアスカは今帰り?」 「そうなのよ、で、シンジが今夜のご飯の材料を買いたいからって、このあた しをつきあわせるのよ。」 「ふふ、そうなの、で、買い物は済んだの?」 「えぇ、まぁ、大方ね。」 「碇くん、今夜は何にするの?」 「うん、アスカが今夜はシチューがいいって言うから・・・」 そんな会話を交わしながら勘定を済ませると3人はスーパーを出た。 「じゃ、わたしはこっちだから。」 「うん、じゃまたねヒカリ。」 ヒカリは自宅の方へ歩きかけて、思い出したように振り返ると2人に聞いた。 「あ、そうだ、明日は学校来れるの?」 「それが行けないのよ明日も、まったく人使いが荒いったら。」 アスカは不満を口にするが、表情は笑っていた。そんなアスカをシンジも笑顔で 見ている。 「そう、碇くんも?」 「うん。あ、でも綾波は行けるはずだよ。」 「わかった、じゃ、2人ともがんばってね。」 「うん、じゃ、また。」 「バイバイ、ヒカリ。」 3人は別れの挨拶を笑顔で交わし、軽く手を振り合って別れた。ヒカリは一人に なると、誰にともなく微笑むとつぶやいた。 「・・・アスカがシチューがいいって言うから・・・か・・・幸せね、アスカ。」 ヒカリは姉妹の待つ家路をいそいだ。 2人はヒカリと別れると、いつものようにアスカ主導で会話を交わしながらマン ションに向かった。街は夕焼けに染まっている。行き交う人々も皆家路を急いで いるようだ。しばらく行くと風船売りの屋台が子供に囲まれていた。母親らしき 大人達が会話を交わしている。 「シンジ、シンジ、風船よ、風船!」 アスカがシンジのシャツの袖を引っ張りながらめずらしいものを見るように言っ た。 「あ、うん、なんだかめずらしいね。」 シンジも風船売りの屋台など見るのは初めてだった。 「買って。」 「え?」 アスカの唐突な言葉に一瞬ついていけないシンジ。 「買ってらっしゃい。」 「ア、アスカ、風船なんか欲しいの?」 「何よ!風船欲しがっちゃ悪い?」 「別に、悪くはないけど・・・」 「なら、さっさと行きなさいよ、バカシンジ!!」 結局シンジは風船を買わされることになった。屋台のまわりには5〜6人の子供 とその母親らしき女性が4人いて、風船の色を選んだり、風船と一緒に売ってい る駄菓子を選んだりしている。 ・・・アスカには、やっぱり赤い風船だよな・・・ シンジは赤いひときわ大きな風船を選ぶと、屋台に並んだ駄菓子を見た。そこに は色とりどりの駄菓子が並んでいる。ふと見ると透明なビンに奇麗な丸いキャン ディが入れられている。キャンディは夕日に照らされて不思議な淡い光をビンの まわりに投げかけていた。青、黄、赤、緑。半透明のキャンディ達は包み紙も透 明なため、とても奇麗に見える。 ・・・なんだか懐かしい感じがするな・・・ ・・・そういえば、昔、母さんにねだって・・・ ・・・あの時は、そう、赤いキャンディ・・・ シンジの脳裏に過ぎ去った遠い思い出が蘇った。幼い頃に母に連れられて出かけ た時、はしゃいだシンジは転んで膝を擦り剥いた。泣き止まないシンジに母は駄 菓子屋で赤いキャンディを買ってくれた。 ・・・あの時のキャンディもこんな奇麗な色だった・・・ 「すいません、この風船と、あと、そのキャンディを、ください。」 「あ、はい、キャンディは何色にしますか?」 屋台の主は愛想よく微笑むとキャンディのビンの蓋をあけながら言った。 「えっと、青と黄色と、赤、あ、赤は二つください。」 シンジは青いキャンディと黄色いキャンディを1つづつ、赤いキャンディを2つ と、アスカの風船を買った。受け取ったキャンディの紙袋をポケットに突っ込む とアスカのところへ戻った。 「シンジ、あんた何買ってたの?」 アスカは屋台から少し離れた所でシンジを待っていたのだが、シンジがキャンデ ィを買ったのを見ていたようだ。 「え、いや、何でもないよ、はい、アスカ、風船。」 「ありがと、で、何買ったのよ。」 アスカは風船を受け取ると一瞬ニコっとして、すぐにシンジの尋問を続けた。 一瞬の『ニコッ』は全てを破壊できるほど可愛いかったが。 「え、別に・・・」 「何よ、隠さなくたっていいじゃない、言いなさいよ!」 「べ、別に隠してなんかないよ、キャ、キャンディだよ・・・」 「キャンディ?」 「うん・・・食べる?アスカ。」 シンジはポケットから紙袋を取り出した。紙袋を逆さまにして手のひらにキャン ディを載せると微笑みながらアスカの方へ差し出した。 「・・・わぁ、奇麗。」 アスカは夕日にキラキラと光るキャンディを見ると、柔らかな微笑みを浮かべて 言った。 「昔、母さんが買ってくれたことがあってさ・・・」 シンジは昔を思い出すように言った。アスカはキャンディを見つめながらその言 葉を聞くと、ちらっとシンジの顔を見上げて言った。 「お母さんは何色を買ってくれたの?」 「え、うん、赤だった。」 「そう、じゃ、あたしは青にする、いい?」 アスカはそう言うとシンジの手から青いキャンディをつまんだ。 それを目の高さまで持ち上げて、軽く首をかしげてシンジに聞く。 アスカのブルーの瞳と青いキャンディが夕日に煌いて・・・ ・・・アスカの瞳って・・・奇麗だな・・・ 「う、うん。」 2人はまた歩き出した。しばらく黙って歩いていたが、アスカが風船を見上げな がらシンジに声をかけた。 「シンジ?」 「え、何?」 「赤いキャンディ、2つ買ったのは・・・お母さんが買ってくれた色だからでしょ?」 「う、うん。」 シンジは何故か恥ずかしくなって真っ赤になってしまった。 ・・・アスカ・・それで青を選んだの・・・ ・・・赤は・母さんの・・僕の思い出だから・・・ ・・・アスカ・・やっぱり頭いいや・・それに優しいな・・・ 2人は程なくマンションに着くと、いつものようにドアの中へ入っていった。 家族のいる家、自分の帰るべき我が家へ。 「ただいまー、あー疲れたー。」 アスカは伸びをしながら自分の部屋へ向かった。シンジは出迎えてくれたペンペ ンを見ながら微笑んで言う。 「ただいま、ペンペン。」 ・・・それにしても・・・綾波は・・何か言いたかったのかな・・・ 「クワッ。」 ペンペンは一声返事をするとリビングに入っていった。シンジはその後ろ姿をぼ んやりと目で追いながらレイのことを思った。 ・・・綾波・・・大丈夫かな・・・ レイは郊外の団地へ続く道を一人歩いていた。夕日が辺りをオレンジ色に染め、 蜩の声が聞こえる。先ほどまでは道行く人を見掛けることもあったが、レイの住 む団地にはきっとレイ以外は住んでいないのセろう、あたりに人影はなかった。 彼女は無表情なまま歩いていたが、その心まで無表情なわけではなかった。しか し、それに気づくことのできる人間はいないだろう、世界中で一人、あの優しい 少年を除いて。 ・・・明日は学校へ行く日・・・ 彼女にとって学校は何の意味もなかった。いや、正確に言えば、『明日の学校』 は彼女にとって意味のないものだった。先ほど意味を失った。 ・・・学校・・・みんながいる学校・・・ 彼女は何故学校に行きたくないのか、自分でもわからなかった。 プラチナブルーの前髪が夕日に煌き、彼女の歩みに合わせてかすかに揺れる。 ・・・明日は・・・ 朽ちかけた団地、彼女はその中の一つに入ると4階まで階段で上り、402号室 のドアの前に立った。一瞬何かを考えるような素振りをしたが、ドアを開けると 中に入っていった。 部屋の中にはパイプ式のベッドと小さな箪笥、箪笥の上には数冊の本、男性用の 歪んだ眼鏡。他にはコンクリートがむき出しの壁と白い冷蔵庫。冷蔵庫の上には 水の入ったビーカーと薬袋に入った錠剤。カーペットも敷かれていない床に、グ レーの椅子が一つだけ。それが彼女の全てだった。 彼女は壁に鞄を立てかけるとベッドにうつ伏せになり目を閉じた。何かに心が圧 迫されるような、締め付けられるような気がする。 ・・・来なくてもいいと言われた時・・・ ・・・悲しく・・なった?・・・ レイは目を開けると枕の上で両手を重ねてあごを乗せた。 ・・・碇くんと・・・弐号機パイロット・・・ ・・・明日も本部・・・ しばらくそうしていたが、目をとじると枕に顔をうずめて両手を枕の下に差し込 んだ。 ・・・碇くんは学校に来ない・・・ ・・・碇くんは学校にいない・・・ ・・・碇くんのいない学校・・・ ・・・碇くん・・・ レイはゆっくりとベッドから起き上がるとカーテンを開けた。夕日が彼女の白い 肌をオレンジ色に染めた。彼女はオレンジ色の部屋の中でも変わらず無表情だっ たが、その紅い瞳は遠くの何かを求める孤独の紅だった。 ・・・寂しいの?・・・わたし・・・ 「あー、おいしかったわぁー。」 ミサトはシチュー皿にスプーンを置くと、満足そうに言った。同時に左手には缶 ビールが握られている。アスカはすでに食事を終えてお茶を楽しんでいる。 「ちょっとミサト、もう3本目じゃない。」 「あら、いいじゃない、食後のビールはまた格別なのよぉ。」 アスカがあきれたようにミサトに言う。シンジはそんな2人を笑って見ている。 葛城家のいつもの夕食風景。 「でも、本当にシンちゃんの料理は最高よねぇ。」 ミサトは上機嫌である。この所ミサトは仕事がそれほど忙しくないので、ちゃん と家に帰って来られるのが嬉しいのだ。彼女にとって家族であるアスカやシンジ と職場ではなくこの家で過ごせるのがなによりなのだ。 「ま、あたしもシンジの料理は認めるわ。」 アスカもお茶を飲みながら機嫌がいい。シンジはそんないつもの風景の中で微笑 んでいたが、何故かふいにレイのことが脳裏をよぎった。 ・・・それにしても・・・ ・・・綾波、やっぱり今日は元気なかったよな・・・ ・・・絶対いつもの感じじゃなかった気がする・・・ ・・・だけど何でこんなに綾波のことが気になるんだろう・・・ すると、それが表情に出たのか、ミサトが声をかけた。 「ん、シンちゃんどうかした?」 アスカもシンジの方を見る。 「い、いえ別に・・・」 「そう?・・・何か心配ごとでもあるなら言いなさいよ?」 「・・・・・・」 「またぁ、シンジのことだからくだらないことで悩んでんじゃないのぉ?」 アスカがからかうように言った。シンジは少しむっとしたような表情で言い返す。 「なんだよアスカ、くだらないことって?」 「さぁーねー。」 アスカは湯飲みを持ってリビングへ歩いていった。TVのスイッチを入れる。 ミサトは少し心配そうな優しい表情を浮かべながら言う。 「なら、いいけど・・・そういえば、ここんとこ毎日テストで疲れたでしょ?」 「いえ、僕は大丈夫です、でも・・・。」 「でも・・・何?シンちゃん。」 「あの、あ、綾波が・・・その・・・」 「レイ?」 ミサトは突然レイの名前が出たので意外そうな表情をした。アスカもレイという 名前を聞いてぴくりと眉が動く。 「・・・綾波が・・・なんだか元気なかったから・・・」 シンジはレイの様子が気になっていたので、そのことをミサトに言った。 「レイが?・・・わたしにはいつもどうりに見えたけど?」 ミサトが思い出すように言う。アスカもリビングから声を投げる。 「ファーストはいつもあんな感じじゃない。どこも変わったとこなんてなかった わよ!」 「そ、そうかな?」 「そんなに気になるなら電話でもしてみなさいよ!!」 アスカが怒ったようにシンジに言うのをミサトは黙って聞いていたが、ニコッと 笑うとシンジに向かって言った。 「アスカの言う通りかも知れないわよ、シンちゃん。」 シンジはミサトのいう意味がわからず聞き返す。 「何が、ですか?・・・ミサトさん。」 「だからぁ、シンちゃん、レイに電話してみたって何もおかしくないってこと。」 「そ、それは・・・」 「レイだって仲間なんだから、心配なら電話くらいしたっていいんじゃない?」 「・・・じゃ、あの・・・ミサトさんが・・・」 シンジは自分で電話をする緊張を想像して、3人の上司であるミサトに電話をさ せようと思って言った。確かにミサトが電話をしてもおかしくはない。 しかし・・・ 「あらぁ、シンちゃんって以外と冷たいのねぇ、レイが心配じゃなかったのぉ?」 ミサトはニヤニヤしながら言う。自分で電話をする気はなさそうだ。と言うより も、シンジに電話をさせたいのだ。 「だ、だってミサトさんだって、綾波の上司なんだし・・・」 「わたしは特にレイの様子、変だと思わなかったもの。」 ミサトにしても本当にレイの様子に気になるところがあれば電話くらいはするだ ろうが、ミサト自身、レイの様子に変わったところを感じていなかったので、シ ンジをからかってビールの肴にしているのだ。 「そんなぁ・・・」 そんなシンジの様子を見て、リビングにいたアスカが苛立ちを隠そうともせずに やって来た。 「もう!あんたは男のくせにうじうじしちゃって何なのよ!!そんなにファース トが気になるなら電話しろって言ってんでしょ!!」 「で、でも・・・」 それでも煮え切らないシンジ。 「でもじゃないわよ!電話が嫌なら、これからあの娘の所行ってきなさい!!」 「わ、わかったよ・・・あとで電話してみるよ・・・」 シンジはアスカに押されたような形でそう言った。だが、その言葉でさらにアス カの機嫌は悪くなった。 「・・・!!・・・わたしお風呂!!!」 アスカは大声でそう言うと自分の部屋へと行ってしまった。部屋のふすまを勢い よく閉める音が響く。シンジは困ったような顔をしてアスカを見送ったが、ミサ トはそんな2人をニヤニヤしながら黙って見ていた。楽しそうに・・・ シンジは時計を確認するとゴクッと唾をのみこんだ。9時14分、この時間なら 別に女の子の家に電話をしても大丈夫だろう。レイの電話番号は記憶している。 今までは一度もかけたことのない電話番号だったが、彼はその番号を忘れたこと はなかった。レイとは同じパイロット同士だから、いつ非常事態が起こってもい いように記憶しているのだと自分を納得させている。しかし、アスカの番号は携 帯電話本体にメモリーしているのに、レイの番号はそうしていななかった。 彼は左手に持った携帯電話を見ると意を決したように右手の人差し指で、その一 時も忘れたことのない番号をプッシュしようとした。 ・・・別に緊張することないじゃないか・・・よし・・・ その時、手の中の携帯電話が鳴り出した。 「うわっ!!」 シンジはあわてて妙な声を上げながら、通話ボタンを押した。 「は、はははい、碇ですけど・・・」 『????、シンジか、俺、相田だけど。』 「ケ、ケンスケ・・・」 『・・・どうした?何あわててんだ?』 「な、なんでもないよ・・・」 電話はシンジのクラスメートの相田ケンスケからだった。シンジは相手がケンス ケだとわかった瞬間に身体から力が抜けていくのを感じた。 『シンジ、どこかに電話するところだったのか?』 「(ぎくぅぅ!)・・そ、そんなことないよ、なんで?」 『いや、いやに早く電話に出たからさ。』 「そ、そうかな?・・・」 ケンスケは中学生の割には勘がいい。相手の心情を思いやる優しさもある。しか し今日はそれがシンジにとっては嬉しくない方向に作用した。 ・・・シンジが電話をするとしたら・・・惣流のワケないし・・・綾波か・・・ 『うん、1コール鳴り終わる前に出たからな。』 「ちょ、ちょうど、電話が手元に、あったからね・・・」 ・・・シンジ、それは電話を手に持っていたってことだろ・・ニヤリ・・・ 『そうか、それはそうと明日学校来るのか?』 ・・・は、よかった・・・ シンジはケンスケの追求が終わったと思って緊張を解いた。だが、それはケンス ケ一流の作戦にハマッたということを意味していた。 「それが、明日もテストで、行けそうもないんだ。」 『そうか、シンジも大変そうだな。』 「うん、でもしょうがないよ・・・」 『そうだな・・・あっと、今日電話したのはいつもの連絡事項なんだけど・・』 ケンスケはクラスの連絡事項を3つほど伝えた。シンジ達はここ3日間学校を休 んでエヴァのテストを行っていたのだ。こういうことはよくあるので、連絡事項 は電話や電子メールで伝達されていた。 『・・・だから、明日の午後の授業では屋外で観察するんだってさ。』 「そうなんだ、わかった、ケンスケありがとう。」 ・・・シンジ、完全にガードを下げたな・・・ニヤリ・・・ 『おっと、こんな時間か、ごめんシンジ、綾波に電話できなくなっちゃうな。』 「え、あ、そうだね、綾波に電話するんだった。」 ・・・ニヤリ・・・ 『ほほう、やっぱり綾波か・・・』 「え!、あ、いや、ケンスケ違うんだ、これは、その・・・」 『今更隠すことないよ、シンジは転校してきた時から綾波を気にしてたじゃない か・・・』 「そ、そんなんじゃなくて、今日綾波が元気なかったから・・・」 ・・・転校してきたときからって・・・そ、そうなのかな・・・ シンジは自分が第3新東京市にやって来た日を思い出していた。第3使徒サキエ ルが侵攻してきた時、誰もいないはずの街で一瞬だけ見えた幻影のような少女。 ・・・あれは、間違いなく綾波だった・・まだ会ったこともなかったのに・・・ 『ま、綾波だってまともに話すのはシンジくらいだしな。』 「え、そ、そうかな・・・」 『そうさ、あの綾波と話すのはシンジだけだよ。』 「・・・けど、綾波は本当は・・その・・すごく優しいんだよ・・・」 『・・・シ・・シンジ・・・』 シンジの言葉はケンスケの想像を超えていた。あのシンジがこれほどはっきりと レイを肯定するとは思っていなかったのだ。数秒の沈黙の後、シンジが口を開い た。 「あ、でもケンスケ、連絡ありがとう。」 『あ、あぁ、シンジもがんばってな。』 「うん、それから、綾波は明日学校行くと思うから。」 『そうなのか?』 「うん、明日のテスト、アスカと僕だけだから。」 『わかった、それから、この間撮った写真、メールで送っといたよ。』 「うん、じゃ、後で見てみるよ、ありがとう。」 『じゃ、またなシンジ。』 「うん、おやすみケンスケ。」 シンジは電話を切ると時計を見て溜息をついた。時計は9時40分。 ・・・今日はもう・・・電話・・・できないな・・・ シンジは机の上のラップトップコンピュータの電源を入れ、ケンスケの送ってく れた写真を見ることにした。 「それじゃ、みんな2人か3人のグループになってください。」 クラス委員長のヒカリの声で教室がざわめきだした。第3新東京市立第壱中学校 2年A組の教室、午後の授業は理科。これから学校を出て生態観察の野外授業で ある。 「えっと、アスカは休みだから、私と一緒にすればいいし、碇くんは・・・」 ヒカリはレポート提出用のフロッピーディスクのラベルに自分の名前とアスカの 名前を書くと、顔をあげて教室を見回した。 「す、鈴原ぁ!」 ヒカリはジャージ姿の少年、鈴原トウジの姿を見つけると声をかけた。 「なんや、イインチョ?」 トウジはヒカリの声を聞くと、ケンスケとの会話を中断して顔をあげた。その瞬 間、ほんのわずかだがヒカリの頬が赤く染まる。 「あの、碇くん、今日休みだから・・・」 「あ、シンジだったらOKだよイインチョ。」 「そや、シンジは大丈夫や。」 ケンスケとトウジがヒカリの言おうとしていることに気づいて答えた。 「そ、そう、それならいいんだけど。」 ヒカリは肯くと、教室を見回した。そしてクラスの責任者らしいよく通る声で言 った。 「じゃあみんな、外へ出てください!!」 その声に答えるように、クラスメート達はぞろぞろと教室を出ていった。それぞ れノートと筆記用具などを持っている。中には携帯用のラップトップコンピュー タを抱えていくものもいた。 <・・・じゃぁ、お前がそれやればいいじゃんか・・・> <・・・でさぁ、その子がまたすごいのよぉ・・・> <・・・うんじゃ、帰りによろか・・・> クラスメートが出ていった教室に一人ぽつんと残る人影があった。彼女は配られ たフロッピーディスクを握り締めて窓際の席からゆっくりと立ち上がると、誰も いなくなった教室を見ていた。プラチナブルーの髪が窓からの風を受けてかすか に揺れている。彼女はその寂しげな紅い瞳をふせると数秒そのまま立ち尽くして いたが、ゆっくりと教室を出ていった。 「初号機、正常起動しました。」 「各部、問題なし。」 「第3から第21までのセンサー、回路開いてください。」 「全センサー、回路開きました。」 ネルフ本部地下施設、第3実験場。オペレーターの声が響く中、シンジはエヴァ ンゲリオン初号機のセンサー調整のため、今日で3回目のエントリープラグの中 にいた。 「センサーの接続を確認しました。」 シンジがコックピットの正面に表示されたホログラフィックディスプレイを確認 して言った。それに答えるように右下のスクリーンにウインドウが開いた。ウイ ンドウにはリツコの姿が映り、from Control の文字が表示される。 『シンジくん、どうかしら?』 「今のところ、問題ないようです。」 『そう、なにか感じたらすぐに言うのよ。』 「はい。」 一方、コントロールルームではスタッフがせわしなく動き回っていた。リツコは ひときわ大きなコンソールの前でスタッフに指示を飛ばしている。 「マヤ、センサーからのフィードバックを通常レベルまで上げて。」 「了解、全センサー、フィードバックをノーマルへ設定します。」 リツコの後輩の伊吹マヤがすばやく指示を実行する。 「シンジくん、今、新しいセンサーを通常の状態にしたわ、どうかしら?」 『はい、問題ありません。』 シンジはエントリープラグの中で新しいセンサーからのフィードバックを感じて いた。エヴァンゲリオンはパイロットとA10神経を通じて接続される。パイロ ットはそれによってエヴァンゲリオンを自分の体のように扱うことができるのだ。 『現在のシンクロ率、84%、ハーモニクス正常です。』 エントリープラグ内にオペレーターの声が響く。 ・・・やっぱり夕べ電話すればよかったかな・・・ シンジは昨夜、レイに電話をしていなかった。ケンスケからの電話でタイミング を逸してしまったのだ。また、ケンスケの送ってくれた写真に写っていたレイの 姿が、一層シンジの心に不安ともつかない影のようなものを残していた。 ・・・いつも綾波はあんな感じかも知れないけど・・やっぱり・・・ ・・・やっぱり、最近の綾波はなんだか・・なんだか・・哀しそうだよ・・・ ・・・どうしてみんな、わからないんだろう・・・ ケンスケの送ってきた写真は4日ほど前に教室で撮った他愛もない写真だった。 教室でふざけるシンジや、アスカ、数名のクラスメート、そこにはレイの姿も写 っていた。 ・・・あの綾波の目は、本当に寂しそうだ・・・ 『シンジくん?』 「え、あ、はい。」 『どうしたの?・・集中してる?』 「はい、大丈夫です。」 『じゃ、プラグ深度を少し深くするから、いい?』 「はい。」 シンジが答えると、身体全体に重さが増したような感覚が起こり、頭の中に口で は言い表せない圧迫感が広がる。思わず目を閉じるシンジ。 ・・・あ・・綾波・・大丈・・夫・・・うっ・・・ <ビー!!> 突然コントロールルームに警報が鳴り響いた。 「どうしたの!?」 リツコの声が飛ぶ。 「パルス逆流!」 「シンクログラフ反転!!」 「パイロット意識混濁!」 次々と報告される状況に対してリツコがすばやく指示を出す。 「プラグ深度を戻して!」 「はい、プラグ深度初期状態です!」 マヤがリツコの指示を的確に実行していく。 「シンジくん、聞こえる?シンジくん!!」 「パイロット意識ありません!!」 「・・・どういうこと・・・」 リツコが思わずつぶやく。今までこの程度のテストは何回も行ってきた。それに 今回のテストが特に危険なわけでもなく、むしろ軽くこなせる範囲のものだった はずだ。リツコは状況を確認するために新たな指示を出す。 「デストルド反応は?」 「ありません、あ!」 「どうしたの!?」 「リビドー反応を確認、異常値です。」 「何なの・・・」 リツコは目の前で起こっていることが信じられないというように言った。 「シンクログラフ正常に戻りました。」 「ハーモニクス確認。」 「初号機正常起動中です。」 「マヤ、シンクロカットできるかしら?」 リツコがマヤに聞いた。マヤは目の前のディスプレイを見つめながら、すばやく 状況を判断すると答える。 「多分、問題ないはずです。」 「そう、じゃテストは中止します、シンクロカット、プラグ強制排出。」 「了解、シンクロカットします、・・・あ、なに?・・・ダメです!」 「どうしたの!?」 「初号機、信号を拒絶、シンクロカット不能、直接プラグに信号を送ってもダメ です!!」 「パイロットは!?」 「パイロット、依然意識不明です、・・・あ、エ、エントリープラグ内の質量変 化を検知!」 「なんですって!!」 リツコの顔が蒼白になった。エントリープラグにはパイロット、この場合はシン ジがいるのだ。エントリープラグ自体は完璧な気密性があり、内部の質量が変化 することはありえない。 「エントリープラグ内の質量がわずかに減少しています・・・」 エントリープラグの内部を映し出しているモニターにはまるで眠っているかのよ うなシンジの姿が映っていた。 シンジは誰かに呼ばれる声を聞いた。とても懐かしい声のような気がした。 <・・・シンジ・・・・シンジ・・・> 「・・・誰か・・・呼んでる?・・・」 はっきりと聞こえるわけではないのだが、頭の中に直接誰かの意識が入りこんで くるような、そんな感じで意味だけが心に浮かんでくる。 <・・・シンジ・・行きなさい・・・> 「・・・誰・・誰なの?・・・」 今度はさっきよりはっきりと感じることができた。確かに誰か、ひどく懐かしい 誰かが語り掛けている。 <・・・シンジ・・行ってあげなさい・・・> 「・・・行くの?・・・どこに・・・」 シンジは自分がどういう状況に陥っているのか、自分がどこにいるのか、全てに ついて不安も感じなければ、疑問すら抱いていなかった。ただ自分の意識の中で 行われる会話だけに集中していた。 <・・・あなたしかいないのよシンジ・・・行ってあげなさい・・・> その言葉と一緒にすべてのイメージがシンジの中に展開していった。言葉ではな く、意味だけが伝わってきて一瞬にしてシンジは理解した。 「うん、そうだね・・・僕、行かなきゃ・・・」 シンジは少し照れたように微笑んだ。 「それじゃ、時間になったらここに集合するように、洞木、頼んだぞ。」 理科の教師はそう言うとヒカリの方を見た。そのまま自分も林の方に歩いて行く。 「じゃ、みんな時間までグループごとに観察してください。今日とそれから明日 の午前中にも時間はあるから。」 各自2〜3人のグループ毎に林の中に入っていく。学校の裏手にある雑木林には 人が歩ける道があり、中学生だけで入っていっても問題はないようだ。 蝉の声がうるさいくらいに夏を感じさせる。 レイは一人で林に入っていった。木々が夏の午後の日差しをさえぎり、少しひん やりする。ところどころに自分と同じ制服が見え隠れしている。みんな何かを話 しながらノートにメモをとったり、スケッチしたり、デジタルカメラで写真を撮 ったりしているようだ。 ・・・今ごろは初号機起動の時間・・・ レイは林の中を歩きながら本部の様子を思い浮かべた。手にはフロッピーディス クしか持っていなかった。じっと耳をすましていると蝉の声に混じってクラスメ ートの話し声が聞こえる。立ち止まって見回すとそこここにクラスメートがいる。 レイのすぐ横をクラスメートが通りすぎる。一瞬目があうが、言葉を交わすわけ でもなく何もなかったように通りすぎてゆく。誰も彼女の存在をその意識にのぼ らせることはない。彼女はそこにいながら誰の目にも映っていなかった。誰も彼 女に話しかけることはない。ふと自分はそこにいないのではないかという気がし た。今までもずっと一人だった。本部でも学校でも、ずっと一人だった。何も感 じなかったし、それが普通だった。 しかし、今は不安だった。 確かに自分はそこに立っているのに、存在していないような気がした。 ・・・碇くん・・・ レイは無表情でその場にいつまでも立ちつくしていた。 「それ、どういうこと!?」 ミサトは語気を荒げてリツコに言った。 「わからないのよ、それが・・・」 リツコの口調は歯切れが悪い。コントロールルームの強化ガラスの向こうには、 拘束具に固定された初号機がこちらを見つめている。コントロールルームのモニ ターはすべて初号機が正常に起動中であることを示していた。 「わからないって・・・初号機は正常なんでしょ。」 「パイロットの意識がないのと、エントリープラグ内の質量が少なくなったのを 除いてはね。」 ミサトは初号機のエントリープラグ内を映しているモニターに目をやった。そこ にはまるで眠っているようなシンジの姿が映し出されている。 「電源をカットして、プラグを強制的に排除したら・・・」 「ミサト、パイロットの意識がないのよ、電源をカットしたらパイロットの生命 維持に問題がないとも言えないわ。」 「じゃ、どうすれば・・・」 ミサトは強化ガラスの向こうの初号機を見つめた。 「自我境界は健在だし、シンジくんの身体自体は正常なの、ただ・・・」 「ただ?」 「・・・ただ・・まるで魂が・魂だけがなくなったような・・・」 リツコの言葉にミサトは一瞬我を忘れて大声で言った。 「何よそれ!・・・リツコ、あ、あんた何言ってんのよ!!」 「すべてのセンサーは正常なのよ!!そして減少したプラグ内の質量は、推測さ れるシンジくんの・・・シンジくんの・・・」 「・・・魂・・・」 コントロールルームに張り詰めた空気がさらに重くなった。 「・・・リツコ。」 「・・・何?」 「碇司令には?v 「・・・報告済みよ。」 「そう・・・」 ヒカリは先ほど集めたフロッピーディスクを確認していた。野外授業が終わり教 室に戻った後、ホームルームや教室の掃除を終えて、大部分の生徒は帰宅したか、 クラブ活動のはずだ。開け放たれた窓からの風が心地よかった。 「えっと、全部名前、あるわよね。」 ヒカリは自分の席に座って1枚ずつラベルを確認していった。こういう名前を書 かなければいけない提出物に名前を書き忘れる人間は必ずいる。しかし、今回は ちゃんとすべてのフロッピーディスクに名前が書かれているようだ。レポートは 2人か3人のグループで1つだけ作成すればいいので、それぞれのフロッピーデ ィスクのラベルにはグループのメンバー2〜3人の名前が書かれていた。 「大丈夫かな。」 今日の野外授業の続きが明日の午前中行われるので、明日の朝もう一度フロッピ ーディスクを配る必要がある。その時にもう一度名前を確認してもいいのだが、 ヒカリの几帳面な性格はそれを許さなかった。 「うん、いいみたい。」 確認作業もほぼ終わりに近づいた頃、教室に誰かが入ってきた。ゆっくりとヒカ リの方に近づく。ヒカリも気配を感じて顔をあげた。ヒカリの黒い瞳と紅い瞳が 交錯する。 「綾波さん、どうしたの?」 プラチナブルーの髪が窓からの風に揺れている。紅い瞳はヒカリをじっと見つめ ていたがヒカリは何も読み取れなかった。レイは左手に鞄を持ち、右手には何か を握り締めている。 「・・・これ。」 レイはヒカリを見つめたまま無表情につぶやいた。 「何かしら?」 ヒカリはレイの右手にあるものに視線を移した。それに合わせるようにレイがゆ っくりと右手を差し出した。それは1枚のフロッピーディスクだった。 「・・・提出していなかったから。」 「あ、そうだったの?」 「・・・ごめんなさい。」 レイは視線を自分の右手に移した。 「ううん、別にいいのよ。」 ヒカリは笑顔で答えると、確認していたフロッピーディスクを奇麗に重ねて机の 上に置き、右手を伸ばしてレイの差し出したフロッピーディスクを受け取ろうと した。ヒカリがフロッピーディスクをつかむとレイは少し躊躇したような様子を 見せたが、ラベルを隠すようにしていた指をゆっくりとはずした。ヒカリがレイ を見上げるとレイの唇がかすかに動いた。 「・・・じゃ、さよなら。」 レイはそう言うと、ヒカリの机に重ねてあるフロッピーディスクをちらっと見て、 教室を出ていく。その表情からは相変わらず何も読み取れない。 「・・・さよなら、綾波さん。」 ヒカリはレイの態度に何かを感じてその後ろ姿を見送った。そしてレイが教室か ら出ていった後、自分の右手に残ったフロッピーディスクに視線を移した。 ラベルには名前がちゃんと書いてあった。 綾波レイ ただ一つだけ。 涼しくなるにはまだもう少し時間がかかる。15年前の大災害は日本を常夏の国 に変えてしまっていた。レイは陽炎が揺れるアスファルトの道を自分の住んでい るマンモス団地へと歩いていた。団地に近づくにつれ人通りが少なくなる。 レイは真っ直ぐ前だけを見て歩いていた。 ・・・わたしは・・・ レイは胸に感じる痛みに立ち止まった。右手を胸にあてて深く息をする。 ・・・わたしは・・・ 目を閉じるとそのままゆっくりと息を吐いた。 ・・・寂しいの?・・・ ・・・どうして?・・・ ・・・いつから?・・・ ・・・碇くんのせい?・・・ レイは目を開けた。誰もいない公園が目の前に見える。ゆっくりと公園に足を踏 み入れると、かすかな風に寂しそうに揺れるブランコに視線を止めた。 ・・・ブランコ・・・ ・・・碇くん・・・ ・・・碇くん・どうして・・・わたしを・・・ ・・・碇くん・・・ ・・・碇くんに・・会いたい・・・ その時、なにかが制服のスカートを引っ張っているのに気づいた。レイが見ると 5歳くらいの男の子が微笑みながらスカートをつかんでレイを見上げていた。 「・・・誰?」 レイの問いかけに男の子は無言で微笑んでいたが、スカートを離して自分の背中 に手を回して身体を揺らしている。視線はレイの紅い瞳を見上げたまま。 「・・・あなた、誰?」 レイの問いかけには答えない。ただニコニコと屈託のない笑みを浮かべている。 レイはそのまま公園から出て行こうとした。すると男の子もトコトコとついてく る。レイは立ち止まって男の子の方を向くと、鞄を膝に抱えてしゃがんだ。自分 の目線を男の子の目線に合わせると優しく言った。 「・・・何しているの?」 「・・・・・・」 男の子は相変わらず微笑んでいる。 レイは知らない人から見れば無表情に見えるかも知れないが、優しい表情をして いた。 「・・・一人なの?」 「・・・・・・」 男の子は微笑むばかりだ。 「・・・お母さんは?・・・お母さんのところに帰りなさい。」 レイはそう言うと男の子の髪を右手で撫でた。 「・・・さびしくないよ。」 初めて男の子が声を発した。まるでレイに言い聞かせるように。レイは思わず男 の子の髪を撫でる手を止めた。 「・・・さびしくないよ。」 男の子はそう言うと、レイの背中に両手を回して抱きしめた。 「・・・優しいおねいちゃん・・・さびしくないよ。」 男の子はレイを抱きしめたまま言った。男の子の腕ではレイをちゃんと抱きしめ ることはできないのだが、一生懸命背中に小さな手を回してレイを包もうとして いる。レイは暖かいものが自分の心をつつんでいくような、そんな気がした。 「・・・優しいおねいちゃん・・・ひとりじゃないよ。」 男の子は精一杯の優しさでレイに言っている。レイにはそれがはっきりとわかっ た。レイは瞳を閉じて言った。 「・・・ありがとう。」 「・・・おねいちゃん?」 男の子はレイの背中から手を放すとレイの顔を覗きこみながら言った。レイは目 を開けると男の子の瞳を見つめた。黒い瞳が優しく微笑んでいる。懐かしい優し さ、誰かに似ている。 「・・・おねいちゃんの目、きれいだね。」 「・・・わたしの・・・目?」 「・・・赤くて、きれいだね。」 「・・・奇麗?」 男の子はレイの頬に手を伸ばすと、白く透き通るような肌に優しく触れた。 「・・・おねいちゃんの、ほっぺた、すべすべしてるね。」 「・・・わたしの・・・頬?」 「・・・おねいちゃんは、優しくて、きれいな人だね。」 「・・・優しい?」 その時、レイの瞳から涙が零れた。男の子はそれを見ると少し悲しそうな表情を した。そしてもう一度、優しくレイを抱きしめて言った。 「・・・おねいちゃん、どうして泣くの?」 「・・・それ・・は・・・」 「・・・おねいちゃん、悲しくないよ。」 「・・・・・・」 「・・・優しいおねいちゃん、泣かないで。」 「・・・う・・ん・・・」 男の子はレイを放すと、小さな手でレイの涙を拭った。その真剣な表情を見て、 レイは思わず微笑んだ。男の子もそれに気づいて微笑む。 「・・・おねいちゃん、笑うともっときれいだね。」 「・・・ありがとう。」 「・・・おねいちゃん、さびしくないように、これあげる。」 男の子はズボンの左ポケットを探ると何かを取り出した。小さな左手を広げると 手のひらにキャンディが3つ。透明な包み紙に包まれた黄色と赤と赤・・・ 「おねいちゃんのきれいな目、おんなじ赤いやつ、だいじなやつ、あげる。」 男の子はそう言うと、右手で赤いキャンディをつまんで、レイの瞳の横にかざし た。 「ほら、おんなじ、きれいな赤だよ、だいじなやつ、あげる。」 男の子はレイの右手をつかんで、赤いキャンディを乗せるとニコッと微笑んだ。 レイもつられて微笑みながら言った。 「・・・ありがとう。」 その時、男の子の笑顔が誰かの笑顔と重なった、レイは一瞬、目の前にいるのが 誰なのかわからなくなった。その時男の子が言った。 「・・・いつもそばにいるからね・・・」 「・・・え?」 男の子はニコッと微笑むとレイの唇に軽くキスをした。そのまま駆け出すとレイ の背後へと足音が遠ざかって行く。レイは一瞬呆然としていたが立ち上がると男 の子の姿を追って振り返った。レイが振り返った時には、すでに男の子の姿も足 音も消えていた。 ・・・碇・・くん? レイの右手には奇麗な赤いキャンディが残っていた。 「先輩!!」 「どうしたのマヤ!?」 ディスプレイを見ていたマヤがリツコに声をかけた。リツコはただならぬマヤの 声に、急いでディスプレイに目を走らせる。 「エントリープラグ内部の質量が・・・」 「どうしたの!?」 ミサトもディスプレイを覗き込む。それと時を同じくしてオペレータの声がコン トロールルームに響いた。 「初号機、シンクログラフ反転!!」 「パルス逆流します!!」 「ハーモニクス消失しました!!」 「現状維持を最優先、パルスの逆流を止めて!!」 リツコの緊迫した声が指示を出す。 「ダメです。パイロット危険区域に入ります!!」 マヤの悲痛な声が答える。それを無視するようにリツコの声が飛ぶ。 「デストルド反応は!?」 「大丈夫です、反応ありません!」 「リビドー反応、急激に減少!通常値に戻ります!!」 「シンクログラフ回復!!」 「パルス逆流止まりました!」 「ハーモニクス確認!!」 「・・・いったい・・・どうなっているの・・・」 リツコの声がわずかに震えている。ミサトは一言も声を発することができない。 「パイロット危険区域を脱出、意識レベル反応あり!!」 マヤの声に、ようやくミサトが反応した。 「シンジくん!!聞こえる!?シンジくん!?」 「パイロット、意識戻ります!!」 「シンクロ率、82%で安定しました。ハーモニクス正常!!」 「初号機、正常起動を確認!!」 「パイロット、脈拍、血圧、全て正常!」 「同じく、意識レベル回復、生命維持に問題ありません!」 「シンジくん!?」 ミサトの声にようやくシンジが反応した。 「・・・あ、あれ・・・ミサトさん?」 「シンジくん!!大丈夫!?大丈夫なのね!?私がわかるのね!?」 ミサトは目を潤ませて、声も涙声になっている。 「・・・はい・・だけど・・どうしてミサトさんがそこにいるんですか?」 「・・・は?」 ミサトもリツコも、そこにいたすべての人々がシンジの問いに唖然とした。 「・・・シンジくん、自分がどうなっていたか・・憶えてないの?」 リツコの問いかけに、シンジは不思議そうな顔で答えた。 「え、何言ってるんですか、えっと、プラグ深度、変えるんですよね?」 「・・・・・・」 リツコは何も言えなかった。 「それじゃ、昨日の続き、やってください!!」 ヒカリが言うと、クラスメート達は学校の裏手の林に向かうべく、教室を出て行 った。アスカも教室から廊下へと歩きながらヒカリに声をかける。 「はぁ、この暑いのに野外授業かぁ。」 「でも、たまには外もいいものよ、アスカ。」 「そうかも知れないけど・・・」 そこにシンジがやって来た。 「ねぇ、アスカ、この授業ってグループでやるんだって、知ってた?」 「え、そうなのヒカリ?」 アスカの問いかけに、ヒカリが思い出したように答える。 「あ、そうなの、アスカはわたしと一緒にしておいたんだけど、いいでしょ?」 ヒカリはラベルに自分の名前とアスカの名前の書かれたフロッピーディスクを見 せながら言った。 「もっちろんよ、ヒカリ!」 「それから、碇くんは鈴原達が確か・・・」 シンジはそれを聞いて納得したように微笑むと言った。 「そう、わかった、僕はトウジ達と一緒だね。」 「えぇ、そのはずだけど。」 「ありがとう。」 シンジはヒカリに礼を言うと、廊下を歩きながらトウジを探した。しばらくして 下駄箱で靴を履こうとしているトウジとケンスケを見つけた。 「ねぇ、トウジ、イインチョから聞いたんだけど、僕も一緒に・・・」 そこまでシンジが言ったところで、ケンスケが驚いたような顔をして言った。 「え、そうか、シンジの事、忘れてたよ、トウジ!!」 言いながら、トウジに目配せをする。トウジもそれを見てニヤリと笑うとケンス ケに答えるように言った。 「そうやった!!すまんのうシンジ、すっかりシンジのこと忘れとったわ。」 「シンジ、レポート、もう2人で書き始めちゃったんだよ、ゴメンな。」 「えぇ、そ、そんな・・・じゃ、僕はどうしたら・・・」 「ほんま、悪いシンジ、じゃ、わいらは行くから、後でな。」 「いや、悪いシンジ、じゃな。」 トウジとケンスケはニヤニヤと気味悪い笑いを浮かべながら行ってしまった。 シンジはしょうがないのでとぼとぼと林の方へと歩いて行った。 ・・・トウジもケンスケも冷たいなぁ、どうしよ、僕・・・ 林の入り口に着くと、シンジは立ち止まって大きな溜息をついた。 ・・・そういえば、綾波、どうしたかな・・・ シンジは歩き出すと無意識に林の中でレイを探した。しばらく林の中を歩いてい ると、レイはすぐに見つかった。林の外れの少し開けた草むらで、一人きりで何 かの花を見つめていた。 「奇麗な花だね。」 ・・・碇くん!!・・・ シンジが声をかけると、びくっと身体を震わせて、レイは振り返った。紅い瞳が シンジを見つめる。 「・・・・・・」 「・・・その、ごめん、驚かしちゃった?」 シンジはレイに見つめられて頬が赤くなるのを感じた。レイもわずかに頬を染め ている。 「・・・いえ、いいの。」 レイは小さな声で答えた。シンジから見ると朝の太陽がちょうど逆光になって、 レイのプラチナブルーの髪がラインライトに煌くように見える。紅い瞳をわずか にふせて、白い頬に夏草が光を反射してキラキラと輝いている。 「あ、あの・・綾波は・・その・・・誰と・・一緒なの?」 シンジはレイを見つめることができなくて、俯いたまま聞いた。レイはその手に 持っているフロッピーディスクのラベルをじっと見つめながら言った。 「・・・わたしは・・・ひとり・・・」 シンジはレイの言葉を聞いて、顔を上げた。 ・・・綾波、ひとりなの?・・・ ・・・よし・・電話はできなかったけど・・・今日は・・・ ・・・今日は・・・ ・・・逃げちゃダメだ・・・ 「じゃ、じゃぁ、あの僕、昨日休んで、誰も組んでくれないから・・・」 レイは俯いたままシンジの言葉を聞いている。 「・・・その、よ、よかったら、僕と、その、組んでくれないかな?」 ・・・碇くん・・わたしを誘ってくれるの?・・・ レイがかすれるような、小さな声で答えた。 「・・・かまわない・・・」 「・・・え、い、いいの?」 シンジは思わず聞き返してしまった。レイの頬が真っ赤に染まっている。 「・・・わたし・・・かまわない・・・」 「・・・そ、そう、よかった・・・」 シンジの言葉にレイがようやく顔を上げてシンジの方を見た。 「・・・碇くん?・・・」 ・・・よかったって、思ってくれるの?・・・ 「はは、あの、綾波、元気なかったから・・・」 ・・・碇くん・・心配してくれるの?・・・ 「だから、綾波と、話したいと思ってたんだ、ずっと。」 ・・・わたしと、話したい?・・・ レイが驚いたような目でシンジを見つめていると、シンジが何かを思い出したよ うに言った。 「あ、綾波、キャンディ食べる?」 シンジは左手でズボンのポケットをさぐると、何かをつかみ出して手をひろげて 見せた。手のひらにキャンディが2つ。透明な包み紙に包まれた黄色と赤・・・ ・・・キャンディ?・・・ シンジは微笑みながら、赤いキャンデイをつまみあげると、レイの瞳の横にかざ して言った。 「綾波の瞳って、奇麗だね、ほら、同じ色のキャンディ、あげるよ。」 レイは思わず小さな桜色の唇に手をあてて、呆然とシンジを見つめた。 ・・・碇くん・・なのね・・・ 「あ、綾波、どうしたの?」 レイの表情にゆっくりと微笑みがひろがってゆく。 ・・・綾波・・やっと笑った・・すごく・・・奇麗だよ・・・ シンジもレイも、ほんの数秒、黙ったまま・・・何かを確かめる。 ・・・わたし・・・ここに・・いる・・・ レイは夏の朝のきらめく光の中で、微笑んだまま言った。 「・・・なんでもないわ・・・ありがとう。」 シンジも微笑んで言った。 「・・・じゃ、そのフロッピーに、僕の名前を・・・」Fin.
−ありがとう− 作者からの感謝の言葉。
カヲルくん、いつもご苦労さまです。アスカちゃん、あんまり活躍させて
あげられなくてゴメンなさい。レイちゃん、愛してます、じゃなくて、いつ
も僕の作品ではメインを演じてくれてありがとう。シンジくん、大変だろう
けど(いろんな意味で)がんばってね。ミサトさんにリツコさん、渋い大人
の演技(なのか?)、感謝してます。ヒカリちゃんにトウジくん、ケンスケ
くん、いつもありがとう、そのうちメインを頼むかもしれないのでその時は
よろしく。他のキャラの方々もありがとう。そして丸山さん、忙しい中、あ
りがとうございます。最後に読者のみなさま、いつも読んでくださって本当
にありがとうございます。これからもがんばって楽しんでいただけるような
作品を書きますので見捨てないでください、おねがいします。
では失礼します。
管理人(その他)のコメント
カヲル「おや、アスカ君は?」
レイ 「今日はあの人はいないわ。いまごろ、双子山付近に碇君がいるという噂を信じてかけずりまわっているから」
カヲル「・・・・ダミー情報を流したね、君」
レイ 「わたしの小説に、邪魔はいらないわ」
カヲル「・・・あははは、なんか鬼気迫る勢い・・・汗」
レイ 「でも、Shinさん、ほんとうにありがとう。わたしはここが落ち着く。まるで碇君の腕の中にいるように」
カヲル「ぼくはシンジ君の腕の中にいるように幸せじゃないよ」
レイ 「あなたもあの人と同じように、わたしを邪魔だと思っているから。だから、そうなのよ」
カヲル「まま、キャンディ、食べるかい?」
レイ 「・・・・赤いキャンディ・・・・碇君のくれたキャンディ・・・・でも、あの人の赤と同じ色・・・・」
カヲル「青いキャンディはアスカ君が食べてしまったからね。むう、そうするとあとはこの紫色のキャンディ・・・・」
さくっ
レイ 「もう、いい。あなたも用済み・・・・」
カヲル「う、ろ、ロンギヌスの槍は、痛い・・・・涙」